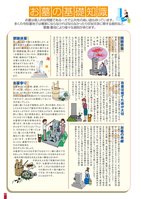横浜あおば霊苑
15/16
お墓は個人的な問題である一方で公共性の高い面も持っています。多くの寺院墓地では檀家にならなければならなかったり宗旨宗派に関する規則など、霊園・墓地により様々な規則があります。■■■■■■■お墓の承継お墓はいわばその家の歴史といえます。また、精神的にも物質的にも大きな財産ともいえるでしょう。それではその財産の相続や後継ぎについてはどのようなきまりがあるのでしょう。お墓の承継は一般の財産の相続とは少し区別されています。民法では「系譜、祭具、墳墓の所有権は、習慣に従って祖先の祭祀を主宰する人が承継する。ただし被相続人が指定に従って祖先の祭祀を主宰するべき人がある時はその人が承継する。慣習が明らかでない時は、前述の権利を承継する人は家庭裁判所が定めるところに従う。」(第八九七条)とされています。お墓はその家の長男が承継することが多いわけですが、長男でなくともその地域の習慣や家族の事情などでお墓を承継する人が決まっている場合には、その人が承継者となります。もちろん女性でもお墓の承継をすることができます。お墓参りお墓参りには、供物、線香、ロウソク、マッチ、花、ひしゃく、スポンジやタオル、ほうき、ちり取りなどを持参します。これらの中には霊園で用意されているものもありますので、あらかじめ確認しておいた方が良いでしょう。お墓に着いたらまず掃除をします。周りを掃き、きれいにしたらタオルなどで墓石の汚れを落とし、最後に新しい水をたっぷりかけ、タオルで拭き上げます。水鉢の水も新しく替え、花と供物を供え、束のままの線香とロウソクに火をつけて焼香、合掌します。お墓参りの後の供物は持ち帰ります。持ち帰ったものはみんなでいただくとよいでしょう。そのままにして帰ってしまうと、腐ったり烏や野良猫などに食い荒らされてしまいます。お参りが終わったら、線香やロウソクの火の後始末も忘れずに行いましょう。お墓参りには小さな子供でもなるべく一緒に連れて行きましょう。子供にはすぐに分からないかも知れませんが、祖先を敬う気持ちを伝える良い機会となります。子供は大人を見て供養のあり方を学び、お墓参りの作法も覚えます。このような日頃の心がけが親から子へ受け継がれて行き、子々孫々に伝わることになるのです。お墓の基礎知識お墓は建てた後が大切お墓を建てることは供養の第一歩ですが、その後も大切です。お盆やお彼岸、忌日などには忘れずに家族などでお参りするようにしましょう。お墓は、祖先や親しかった人が眠るところです。お盆やお彼岸に限らず、家族の誕生や病気が治った時、入学、卒業などいつでもけじめのある毎にお参りしたいものです。家族が無事に暮らしていることを報告し、先祖に感謝する気持ちを伝え、思いを馳せることが何よりの供養といえるでしょう。お墓が近くにある場合は、仏壇に向かうのと同じように毎日お参りしてもかまいません。開眼供養墓石を単なる石からお墓にするために「開眼供養」を行います。開眼とは「仏像の目を開く」という意味で、新しい仏像などができた時に仏の霊を迎えるために行うものです。墓地に親族などが集まってお墓の清掃をし、供物を供えてお経をあげてもらいます。開眼供養は「お魂入れ」や「お墓開き」ともよばれ、四十九日や一周忌などの法要やお盆、お彼岸に合わせて営まれることがほとんどですが、あらかじめお墓を建てておきたいという人も多く、世前中に行うことも珍しくありません。その場合は慶びの仏事として扱われるのが一般的ですから、招かれた際の金封は紅白の水引きがかかったものに「御建碑御祝い」などと表書きをいれるのがよいでしょう。閉眼供養引っ越しなどの様々な事情により、お墓を改葬する場合には開眼供養とは反対に、墓石をただの石に戻すための「閉眼供養」をします。閉眼供養は「お魂抜き」ともいわれ、開眼供養と同様、親族などで集まり、お墓にお供えをしてお経をあげてもらいます。魂を抜かれた古い石はお寺や墓地などで然るべき処理がなされます。15
元のページ